Aさん:最近、なんだか気分が落ち込むことが多くて…。でも、無理に笑顔を作るのも違和感があるんだよね。
Bさん:でもさ、心理学では『笑顔でいると幸せを感じやすくなる』って言うよね。最初は作り笑いでもいいんだって。
Aさん:えっ、それって本当?
私たちの心と行動は密接につながっています。心が行動を動かすこともあれば、逆に行動が心に影響を与えることもあるのです。これは「認知的不協和」と呼ばれる心理効果によるものです。
1. 認知的不協和とは?
認知的不協和(Cognitive Dissonance)とは、「自分の考えや気持ち」と「自分の行動」が一致していないときに生じる不快感のことを指します。
例えば:
- 健康に気をつけたいと思っているのに、ついジャンクフードを食べてしまった。
- 怒っているはずなのに、表情は笑顔を作ってしまう。
このような矛盾が生じると、人は無意識に「行動」と「気持ち」を一致させようとします。その結果、行動が気持ちに影響を与えることがあるのです。
2. 作り笑いでも効果がある?
「笑顔」と「幸せ」の関係を示す実験は数多く存在します。その中でも有名なのがペンをくわえる実験です。
- 方法:ペンを横向きにくわえることで、無理やり笑顔の筋肉を動かす。
- 結果:笑顔の筋肉を動かしたグループは、そうでないグループよりもポジティブな気持ちになった。
たとえ作り笑いであっても、表情筋の動きが脳に「自分は今、楽しい」と信じ込ませる効果があるのです。
3. 笑顔を日常に取り入れるコツ
① 鏡の前で笑顔を作る
1日の始まりに、鏡の前で笑顔を作ってみましょう。最初はぎこちなくても大丈夫。続けることで自然とポジティブな気持ちが湧いてきます。
② 笑顔の「きっかけ」を作る
- 好きな音楽を聴く
- 面白い動画を見る
- ペットや植物と触れ合う
小さな「笑顔の種」を日常に散りばめることで、自然と笑顔が増えていきます。
③ 感謝の気持ちを言葉にする
感謝の言葉を口にすると、自然と笑顔になりやすくなります。
4. 認知的不協和を活用したポジティブ習慣
- 行動から変える:「気分が乗らないからやらない」ではなく、「まずは少しだけやってみる」と考える。
- 小さな成功体験を積む:「5分だけ勉強しよう」「1ページだけ本を読もう」
行動が伴うことで、気持ちも後からついてきます。
5. 笑顔がもたらす効果
笑顔には、私たち自身だけでなく周囲にも良い影響を与える力があります。
- ストレス軽減:笑顔はストレスホルモンを減少させる。
- 人間関係の向上:笑顔は他人に安心感を与える。
- 自己肯定感の向上:笑顔が増えることで、自信が生まれる。
6. 無理にポジティブにならなくても大丈夫
「無理に笑顔を作るなんて…」と思うこともあるでしょう。でも、それは自然な感情です。無理にポジティブにならなくても、「少しだけ笑顔を意識してみる」だけで十分です。
- 笑顔が自然に出る瞬間を増やす。
- 心地よい時間を増やす。
これだけでも、心の中に小さな変化が生まれます。
まとめ:小さな笑顔から始めよう
認知的不協和の心理を上手に活用することで、日常にポジティブな変化を取り入れることができます。
次に気分が落ち込んだときは、無理にでも「にっこり」と笑ってみてください。その小さな笑顔が、心を少しだけ軽くしてくれるかもしれません。
この記事が役に立ったら、ぜひシェアやコメントで感想を教えてくださいね。


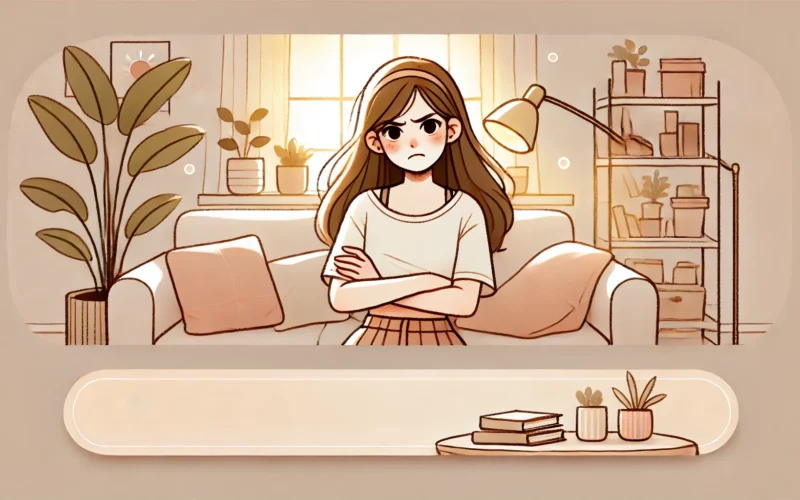
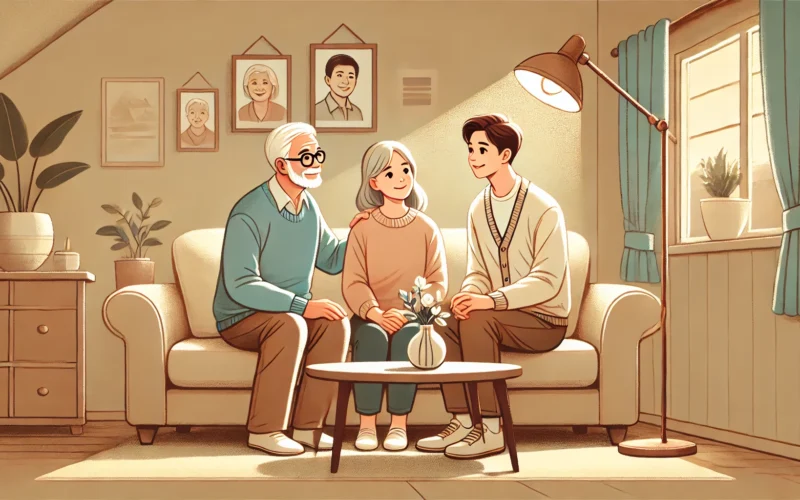
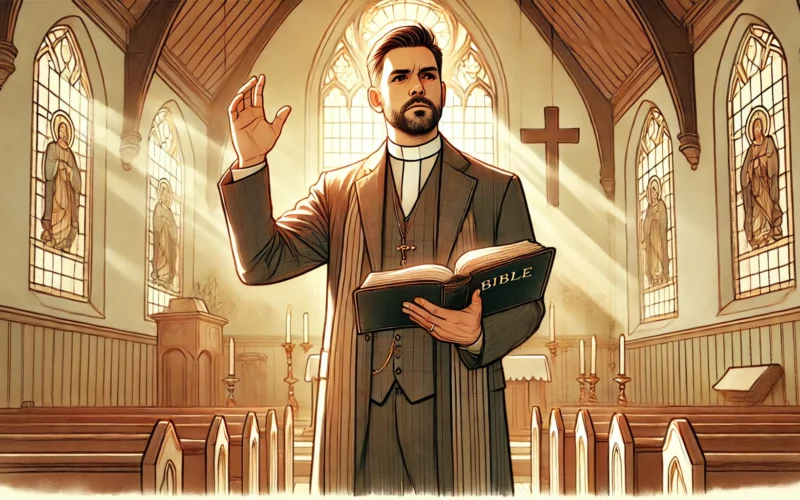
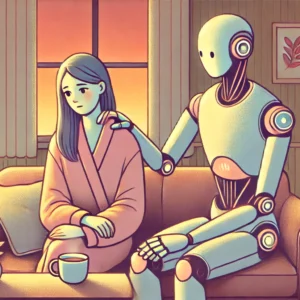
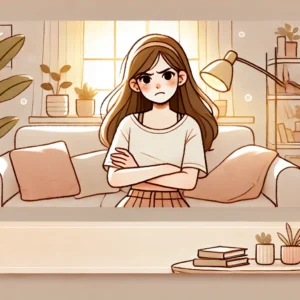

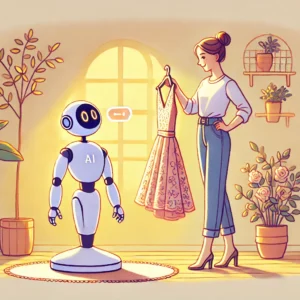

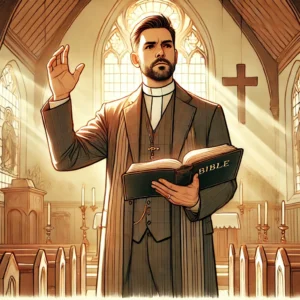


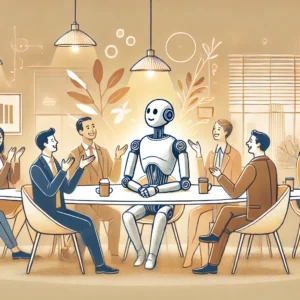

コメント