日常の会話や仕事で、思ったように自分の意図が伝わらないと感じたことはありませんか?
「説明が長すぎてわからない」「何を言いたいのか曖昧」というフィードバックを受けた経験がある方も多いでしょう。
そんなとき役立つのが、「わかりやすさの技術」です。
この記事では、簡潔で伝わる表現を身につけるための方法をご紹介します。
なぜ「わかりやすさ」が大切なのか?
わかりやすい表現は、コミュニケーションを円滑にするだけでなく、信頼関係を深める力があります。
例えば、以下のような場面を想像してみてください。
- 職場の会議で提案内容が伝わらず、何度も質問される。
- 友人との約束が伝わらずに誤解が生まれる。
- 家族との会話で、説明不足が原因で不安や混乱を招いてしまう。
どのケースでも、わかりやすさを意識することで解決できる可能性があります。
わかりやすい表現の基本原則
1. 一文一意を心がける
複数の情報を詰め込むと、相手は混乱してしまいます。
一つの文では一つのメッセージを伝えるようにしましょう。
例:
悪い例:「プロジェクトは来週から始まり、締め切りは2週間後で、メンバー全員が参加します。」
良い例:「プロジェクトは来週開始します。締め切りは2週間後です。全員の参加が必要です。」
2. 具体例を挙げる
抽象的な言葉は避け、具体的な例や数字を使って説明すると、相手にイメージが伝わりやすくなります。
例:
悪い例:「会議の進行が遅れている。」
良い例:「会議は予定より30分遅れています。」
3. 専門用語を避ける
相手の理解度に合わせた言葉を選びましょう。
専門用語を使う場合は、簡単な説明を添えるのがポイントです。
例:
悪い例:「ROIが低いです。」
良い例:「投資に対する利益(ROI)が少ないです。」
4. 視覚的に整理する
リストや箇条書きを活用すると、情報が整理されてわかりやすくなります。
例:
悪い例:「準備するものは、ノートパソコン、充電器、資料、それから会議室の予約です。」
良い例:
準備するもの:
- ノートパソコン
- 充電器
- 資料
- 会議室の予約
わかりやすさを鍛える練習法
1. 他人に説明する機会を増やす
何かを説明するたびに、「本当に相手に伝わったか」を意識してみましょう。
家族や同僚に新しい情報を説明するとき、相手の反応を確認しながら説明を調整することで、わかりやすさのスキルが磨かれます。
2. フィードバックをもらう
説明後に「わかりやすかったですか?」と質問し、相手からのフィードバックを受け取る習慣をつけましょう。
特に、どの部分が理解しにくかったかを尋ねることで、自分の改善ポイントが見えてきます。
3. 文章を削る練習をする
伝えたいことを一度書き出し、その後で削る練習をしてみましょう。
修飾語を減らし、主張をシンプルにすると伝わりやすくなります。
例:
元の文:「私は昨日、近所のカフェでとても美味しいコーヒーを飲みましたが、そのコーヒーは特別な豆を使っていて、非常に印象的でした。」
削った文:「昨日、近所のカフェで特別な豆の美味しいコーヒーを飲みました。」
まとめ:わかりやすさを習慣にしよう
わかりやすさの技術は、練習と意識次第で誰でも身につけられます。
以下のポイントを日常で試してみてください。
- 一文一意を意識する。
- 具体例や視覚的整理を活用する。
- フィードバックをもとに改善する。
これらを習慣にすれば、仕事や日常のコミュニケーションがスムーズになり、人間関係の改善にもつながります。
あなたの工夫している「わかりやすさの技術」はありますか?コメント欄でぜひ教えてください!
この記事が役立ったと思ったら、シェアしていただけると嬉しいです。😊





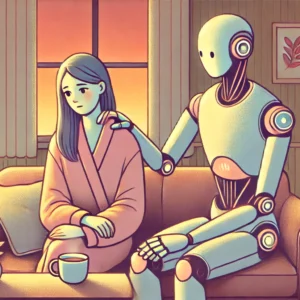
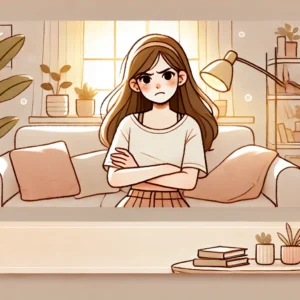

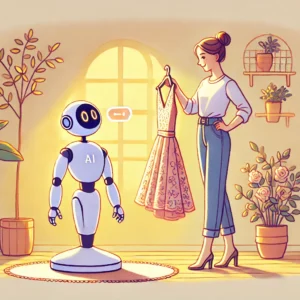

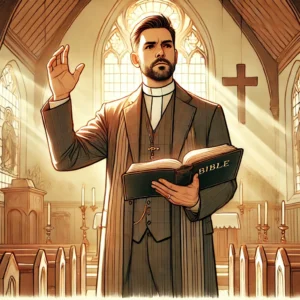


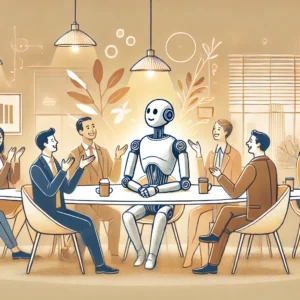

コメント